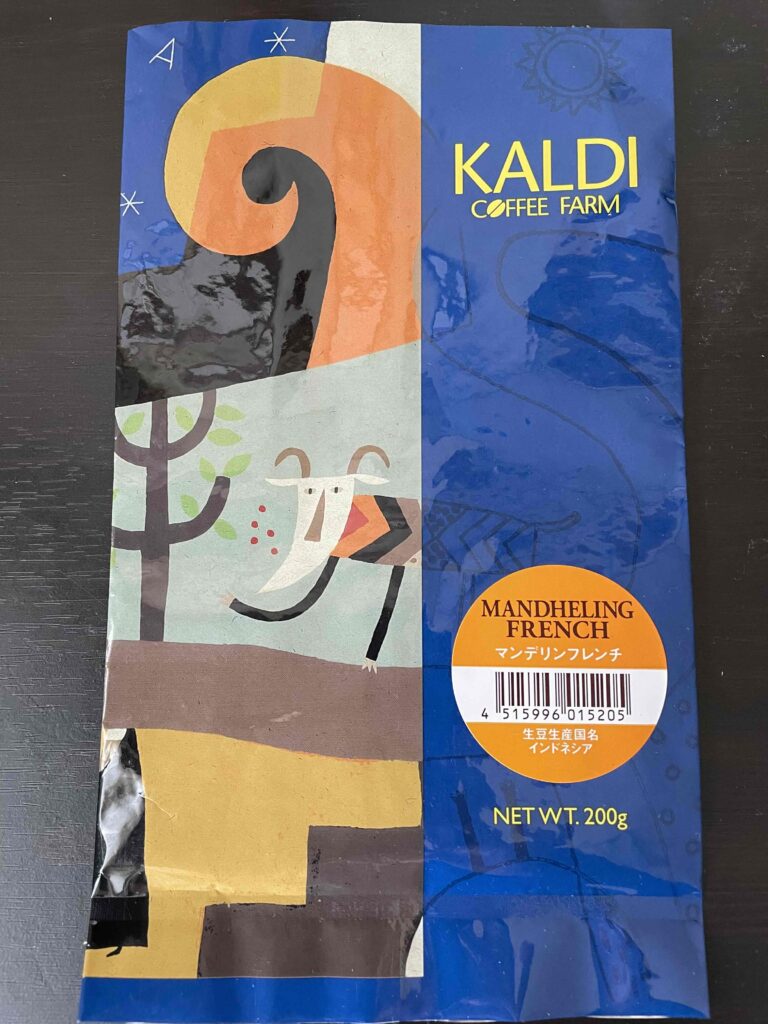こんにちは
こちらは「アマドコーヒー」です!
今回は“コーヒーのギモン”
「コーヒーの漢字”珈琲”の由来」
について取り上げていきます。
当ブログを運営する
インドネシアコーヒー専門店
「アマドコーヒー」
立ち上げまでのストーリーをアニメ化!
インドネシア人青年と
コーヒー飲めないパートのおばちゃんが
コーヒー会社を設立する
当社の設立時期の実話に基づいた物語です。
<登場人物>

アマド(主人公)
インドネシア スマトラ島でコーヒー農園を営む青年。
お父さんと兄弟たちと協力してコーヒー栽培をしている。
アマドの夢は
「自分の農園のコーヒーを日本で広める事」
夢を叶えるために
インドネシアの日本語学校で勉強に励み、
ついに日本に渡るチャンスを得た。
アマド青年の日本での挑戦がはじまる。
コーヒーを漢字で書くと
「珈琲」になることは
みなさんも何となく知っていると思います。
私も書けませんが、読めるぐらいに
「珈琲=コーヒー」
ということは知っていました。
ただ、なぜこの漢字が当てられているのか?
知っている方は少ないでしょう。
そこで今日の記事では
「コーヒーの漢字”珈琲”の由来」
について取り上げていきます。
珈琲の由来は江戸時代

コーヒーに「珈琲」の漢字が当てられたのは
江戸時代だと言われています。
そもそも、
コーヒーが日本に初めてもたらされたのも
江戸時代であり
鎖国下の長崎・出島にオランダ人が
持ち込んだと言われています。
その後、
コーヒーは日本全国に広まる訳ですが、
その過程で津山藩(現在の岡山県津山市)の
蘭学者が「珈琲」の字を当てたようです。
宇田川榕菴と珈琲の意味

コーヒーに「珈琲」の字を当てたのは
津山藩の藩医であり、
蘭学者でもあった
宇田川榕菴(ようあん)だとされています。
宇田川榕菴は化学や自然学、洋学などにも
精通していて、様々な書物を残しています。
コーヒーについての書物である
『哥非乙説』(こひいせつ)も書いており、
日本人向けにコーヒーを紹介した書物だとされています。
珈琲の漢字の意味
コーヒーの漢字が「珈琲」になったのは
『コーヒーの実』の姿かたちが由来と
なったと言われています。
コーヒーの実はこのような見た目をしています。

この赤い実が
女性が髪の毛につけていた髪飾りに似ていた
そんな所に目をつけた宇田川榕菴が
髪飾り・かんざしを意味する「珈」
髪飾りを留めていた紐を意味する「琲」
この2文字を当てて「珈琲」としたようです。
コーヒーの実を髪飾りに見立てて
「珈琲」の字を当てる
宇田川榕菴のセンスは素晴らしいですね。
「可否」「架非」「黒炒豆」など流行らなかった当て字も

今でこそ
「珈琲=コーヒー」が浸透していますが、
「珈琲」以外にも
コーヒーの当て字はいくつも存在していました。
「可否」や「架非」
これはなんとなくコーヒーと読めますね。
面白い当て字が「黒炒豆」
そのまま読むと“黒い炒めた豆”
焙煎されたコーヒーの豆は黒いですもんね。
想像が出来てしまうところが
とても興味深く、面白いです。
しかし、これらの当て字はあまり流行らず
現在、一般的に使われているのは
宇田川榕菴が考案した「珈琲」と
なっている訳ですね。
当て字にも流行る流行らないがある所が
現在にも通じるところがあって
当時の人に親近感が湧いてきますね。
たしかにコーヒーの実を髪飾りに見立てた
「珈琲」のセンスは頭一つ抜けています。
このような由来や経緯があって
コーヒーの漢字表記は「珈琲」に
なっているのです。
まとめ

今回は
「コーヒーの漢字”珈琲”の由来」
について解説をしてきました。
最後までご覧いただきありがとうございました!
当ブログ「アマドコーヒー」では
インドネシアコーヒーについての情報を
日々発信しています。
ぜひ他の記事もご覧くださいね!